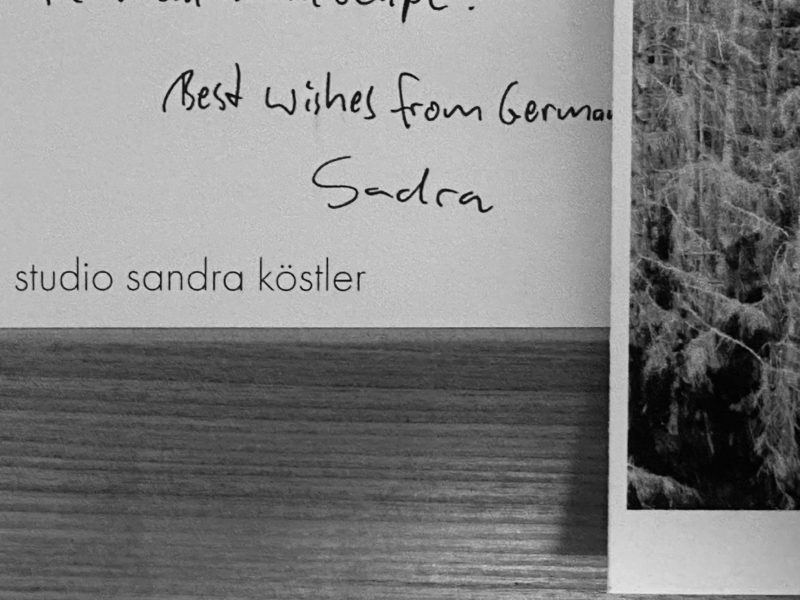「おっと。個人用ではないアカウントから送ってしまった。ドイツは早朝 :)」。ドイツから寝惚けた様子を装って誕生日祝いのメッセージを送ってくれたのは、社会学博士号のビジュアルアーティストで、ボーイッシュなベリーショートのサンドラさんだった。目覚めて最初に思い浮かべた人よ、というロマンチックなラブレターではない。ソーシャルアカウントを切り替え忘れただけかもしれないし、女性のサンドラさんがワイフと呼んでいる男性パートナーの目を盗んで送ったものかもしれない。あるいは博士の愛嬌かもしれないし、本当に夢うつつだったのかもしれない。その粋な計らいに、僕は日本時間の夜に感謝を伝えて、最後にひとこと付け加えた。「おっと。もう夜の十時。もうすぐおやすみ :)」
もうひとりのドイツ人、写真家のカローラさんは、僕のソーシャルアカウントにコメントをくれた。「あなたの文章には村上春樹のようなひねりを感じる」。カローラさんはその後、日本語版があるかどうかはわからないけれど、と前置きしながら、ダイレクトメッセージでおすすめの海外小説をいくつか教えてくれた。「私はノンフィクションを読むことが多いけれど。ムラカミ以外に日本人作家はいないの?」。僕はカローラさんに訊いた。「ハルキムラカミはドイツでも有名?」。カローラさんは日本人相手に気の利いた返信をくれた。「キッコーマンのソイソースよりかは有名だと思う :)」
八十年代の後半、高校生の頃に好んだ小説は田村隆一訳のロアルド・ダールだった。十年以上の縁が続くブリストルの写真家ロイドは、そんなイギリス人らしい皮肉やブラック・ユーモアはあまり口にしない。彼は三脚にセットしたカメラの上から何の変哲もない透明なビニール袋をすっぽり被せて、そこにひとこと添えた。「全天候型カメラケース、パテント・ペンディング」。語尾にスマイルマークをつけないところも、ペンディングにするあたりにも彼の控えめな人柄が表れているのかもしれない。いずれにせよ、ユーモアは世界共通かもしれないし、類は友を呼ぶのかもしれない。かもしれないが多すぎるかもしれないと小説で書いていたのは村上春樹だったかもしれない。
背後に銀色のジャガーが見えた。その隣にはブルーのトヨタ・プリウスが駐まっていた。その二台が隣り合って並ぶと、歯並びの悪い人が口を開けて笑っているみたいに見えた。/『騎士団長殺し』村上春樹