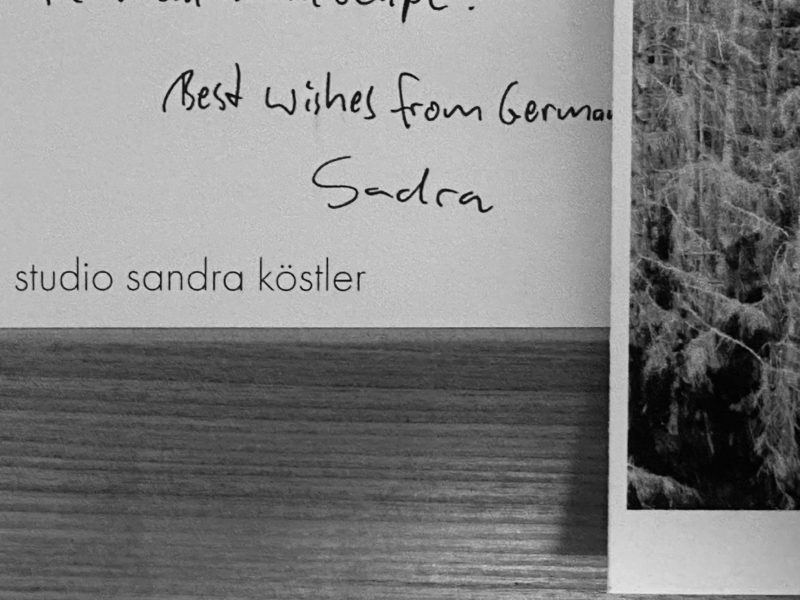「ノンフィクションは嫌いじゃないんですけどね」とポッドキャストにゲスト出演した海外文学の翻訳家の岸本佐知子さんは、まるで魚座の習性を代弁してくれる天の声のように言った。「現実が嫌いなんですよ、私は」
TBSラジオ アフター6ジャンクション「ブック・ライフ・トーク」feat. 岸本佐知子
魚座O型同士の高校文系クラスの同級生は黒縁メガネをかけていた。彼は大学の文学部へ進学した三十数年前、人知れず創作SF小説に挑んでいた。当時彼は、見たこともない未来とか宇宙を舞台にした作品を書きながら、まるで自己弁護するように言った。「小説家っていうのはさ、見てきたようなウソを書く人のことを言うんだよ」
おまけに魚座でO型だが/『わからない』岸本佐知子
「言い得て妙」と僕は頷いた。「歴史小説が、なぜ小説なのか」
「だろ?」とその同級生はインテリジェンスな文豪気取りでメガネのブリッジを指で押し上げながら言った。「何百年とか何千年も前のことなんて、現代人の誰が見たって言うのさ」
歴史って、もう済んだ話じゃん。ネタバレしてるじゃん。/TBSラジオ アフター6ジャンクション「ブック・ライフ・トーク」feat. 岸本佐知子
世間は魚座星人に少なくない偏見を持っている。宇宙人とか不思議ちゃん、ズレているとか頭がおかしいと世間は何かと魚座星人を揶揄せずにはいられないようだ。しかし、三十年前のその頃、魚座の同級生はまるで宇宙人が見てきたように地球の未来を予見していた。
「みんな風邪を病気とは思ってないだろ? 風邪くらいで休むなと言う人もいるくらいだし。でもそのうち、風邪薬が効かないくらい風邪菌が進化して、風邪こそが一番怖い病気になるんだよ。風邪なんて誰もが感染するんだから、そうなったら人間なんて、たちどころに滅亡だよ」
「いつもそんなことを考えてるのか?」とは魚座の僕はさすがに聞けなかった。
「地球人のふりをしている宇宙人の気持ち」が、その後の人生でずっとついて回ることも、この時はまだ知らない。/『わからない』 岸本佐知子